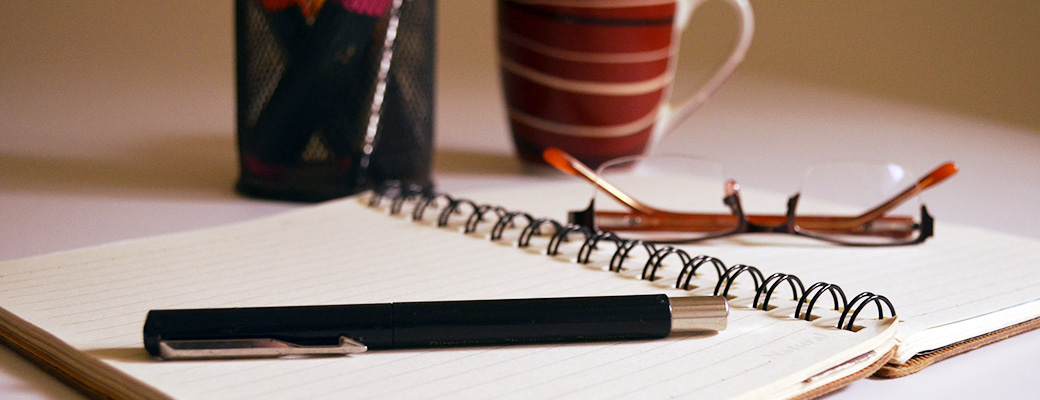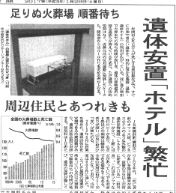超犯罪社会を生きる
「警察白書」によれば、2012(平成24)年に、高齢者が被害を受けた犯罪認知件数(※)は約13万件に上る。認知件数に占める高齢者の割合は増加の一途をたどっている。空き巣やひったくり等に加えて、「オレオレ詐欺」にデジタル技術を加えた新手の詐欺や高齢者の心を巧みに突く犯罪も増えている。
「私だけは」、「オレは大丈夫」と思い込まず、「超犯罪社会」を無事に生き抜く術を身につけよう。
※犯罪認知件数とは
警察が把握した犯罪の発生数のこと。警察官は、犯罪現場の状況から「事件」と判断した場合、被害届の提出を受け、これを認知件数として計上する。事件の「発生数」とは異なる指標。例えば、性犯罪に関する被害などの場合、被害者が被害届を出さず認知されないケースも少なくない。検挙数を認知件数で割った数値が解決率を示す「検挙率」になる。
買う前にちょっと、待って。
その商品、「本当に効果ありますか?」
訪問販売や電話勧誘販売だけでなく、新聞折込チラシの通信販売、インターネット通販と「これを買ってください!」という「品物情報」が溢れている。
どの商品も非常に魅力的に、その効果(効能)が書かれているが、鵜呑みにするのは少し待とう。
悪質商法問題の専門家、エクステージ総合法務事務所・水口結貴行政書士にどんな商品(問題)があるのか、をうかがった。
羽毛布団
多くの人を会場に集め、熱狂的な雰囲気を演出で高額商品を売る「催眠商法」。販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「これ、欲しい人?」などと、最初は安い日用品をプレゼントする。会場で「ハイ、ハイ」と手を上げさせることから「ハイハイ商法」とも言われる。その催眠商法の典型的な商品が「羽毛布団」だ。ほとんどの場合、数十万円~と高額な物が多い。中には「“磁気”が体にいい」などと言って、磁気マットレスや磁気布団が売られる場合もある。
高電位治療器
一定の効果が認められていて、薬事法では「管理医療機器(クラスII)」に分類されている。しかし、販売方法が問題になることがある。本来の効果は「頭痛・肩こり・不眠症や慢性便秘の軽減」のみとされている。しかし、催眠商法の現場では、「血をきれいにする機械」、「血液をサラサラにする」などの説明がある場合も。さらに、具体的に効果がある(症状が改善した、治った)として、「リウマチ、高血圧、アトピー、肝硬変」から「半身まひ」まで、効能効果のオーバートークがされることもあるようだ。
協力:水口結貴行政書士
エクステージ総合法務事務所代表。消費者問題の第一人者として、数々の悪徳商法の相談を受けてきた。8万件以上の解決実績を持つ。
「悪質商法に騙された場合でも、クーリングオフなどで解約ができます。あきらめずに専門家に相談をしてください」と話してくれた