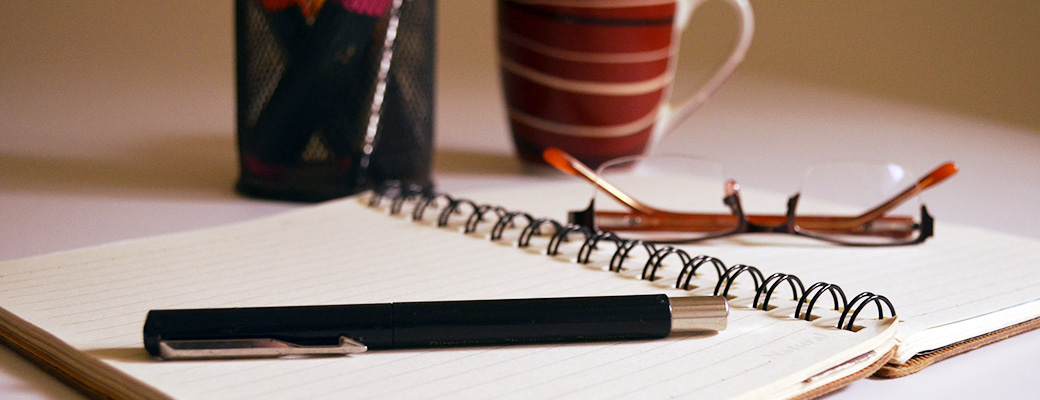若者を狙った悪質商法が横行している
専門家に対策を聞いた
「消費者の権利」、「消費者教育」というテーマで、悪質商法の被害にあいやすい若者に注意点等を専門家に解説してもらった。
「契約」という言葉から、どんな事を思い浮かべますか?
契約書を作る、そこにサインや印鑑を押す…。一般的にはそんなイメージだ。しかし「契約」はそれだけではない。法律上は、品物を買うことも「契約」、言葉で約束するだけでも「契約」とみなされる。契約について正しい知識を持ち、消費者の権利について考えてみる。
お互いが納得の上で交わした契約であれば、その契約を一方的に取り消すことはできません。しかし騙されたり、強制されたりして納得いかないまま契約をした場合もあります。そんな時、どうすればいいのか、悪質商法の専門家・エクステージ総合法務事務所・代表行政書士の水口結貴さんに聞いた。
なぜ「悪徳商法」なのか? 悪徳商法の専門家が特徴を解説
水口結貴さんによれば、本来、契約というものは自分の意志で自分から店や商品に近づいていくのに対し、悪質商法は「売る側から一方的に近づいてくる」のが特徴の1つだ、ということだった。次に、悪質商法の特徴として、「だましたり強制したりして契約させること」をあげてくれた。これは、「帰りたい」と言っているのに帰さなかったり、「不要だ」と言っているのに、何時間も密室でしつこく勧誘して、契約書を書くまで帰さなかったりということ、と教えてくれた。
また、最近では10代・20代の若者をねらった悪質商法も増えている。被害者に話を聞くことができた。
女性の好意を利用した悪質商法。その実態
Aさんは、2年前インターネットを通じて「ジュエリーデザイナー」を名乗る男性と知り合った。その男性からデートに誘われ、デートの後、男性が仕事で使っているという事務所に連れていかれた。男性は「自分がデザインした」というアクセサリーを持ち出し、「あと1つ売れれば、売上がNO1になるから協力してほしい」とAさんに購入を迫ってきた。この男性に好意を持ち始めていたAさんは、最初断っていてものの、結局80万円のネックレスを買う契約をしてしまった。しかし1ヶ月経ってもネックレスは届かず、男性との連絡も取れなくなってしまった。これは「デート商法」と呼ばれる手口で若い女性の被害が後を絶たない。
そのほか街頭で人に声をかけ、商品やサービスを売る「キャッチセールス」にも注意したい。中には、嘘をついたり無理やり商品を購入させるなどの強引な方法が問題になっている。
街頭で声をかけられ、断っているにも関わらず腕をつかまれ無理やりビルの中に連れ込まれた、という女性や、歩いていた所に「サンプルをあげるから」と言われて、ついていったところ、担当者が現れ、長時間に渡り化粧品の勧誘を受けた上、「いらない」と言うと相手が怒り出して不快な思いをしたという。
国民生活センターによれば、2005年度のキャッチセールスに関するトラブルは6,898件にものぼる。そのうち80%を10代・20代の若者が占めている。
突然、身に覚えの無い電話。そこに悪質商法の罠が
Bさんは独り暮らしを始めたばかりの時、ある電話を受けた。第一声は「当選おめでとうざいます」。商品が当たったので取りにきて欲しいと言われた。Bさんは心あたりが無かったものの、無料でもらえるなら…と指定された場所に行ったところ、当たったという商品の話はなく「3万円払えば、もっといい化粧品が手に入る」と言われ、商品を買わされてしまった。これは「アポイントメントセールス」という手口。狙われるのは独り暮らしの若者が多く、卒業生名簿等を悪用している場合もあるとみられます。
販売目的を隠して、独り暮らしの部屋にあがりこむ悪質業者
独り暮らしのCさんは、ある日「布団の無料点検」という訪問を受けた。男は部屋に上がり込み、Cさんの布団を調べ始めた。そして「この布団はダメです」「ぐっすり眠れないですよ」等と言い、新しい布団を売りつけてきた。訪問販売では、必要無い物を強引に売りつける場合があり若者の被害も少なくない。
「訪問販売では、自宅を知られているため「仕返しをされるのではないか」と、怖くなって契約をしてしまう場合が多い」と水口結貴行政書士は指摘する。
この他、架空のもうけ話を持ちかけ、高額な商品を買わせる「マルチ商法」等、悪質商法の手口は様々だ。
納得できない契約をしたときの強い味方 「クーリングオフ」
もしも納得できない契約をしてしまった場合、その契約がまず、クーリングオフができる契約かどうか確認すること。クーリングオフができる場合は、必ず法律で決められた期間内に手続を行うこと。もしもクーリングオフができない場合でも、業者の対応や契約書の内容に不備があれば、消費者契約法等で解約できる場合もある。諦めずに、早めに法律専門家に相談することが大切だ。
クーリングオフは、必ずハガキ等の書面で行い、簡易書留か配達記録郵便等、記録が残る手段で送る。くれぐれも、電話等で簡単に済ませようとはしないことも重要。口頭のやりとりでは、後々「言った・言わない」の議論が出ても証拠が残らず、消費者が不利になってしまうからだ。
契約を交わす前によく考えること。
そして、被害にあった場合は法律専門家に相談すること。この2つを徹底したい。