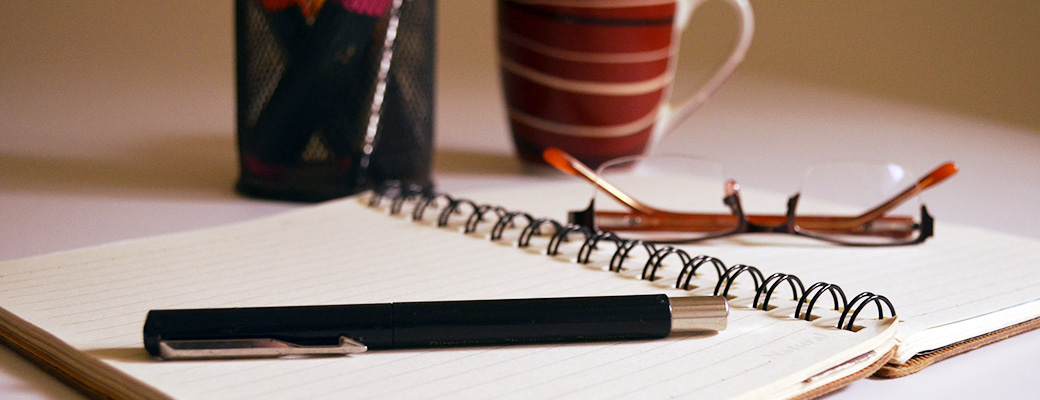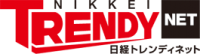IT起業、アフィリエイト、地デジ…。
悪質業者は「旬な話題」で、人をだます
2008年7月、カタログ通販大手の「ベルーナ」が、特定商取引法違反で経済産業省から6カ月間の業務停止命令を受けた。高額な呉服などを販売する目的を隠して展示会に消費者を勧誘していたのに加え、営業員などが複数で消費者を取り囲んで強引に契約を結ばせたりしていた。さらにクーリングオフ期間内なのに、クーリングオフを受け付けなかったなど悪質な販売方法が問題となった。悪質商法の現状を探った。
消費者問題の専門家いわく「悪質販売の手口に変化なし」
国民生活センターによると、消費生活相談の数は、5年連続で年間100万件を超えているという。そして、通信販売や訪問販売、電話勧誘販売など、いわゆる「店舗外販売」相談の半数以上を占める。
悪質商法問題の専門家、行政書士エクステージ総合法務事務所 代表行政書士の水口結貴さんは、「悪質商法の手口は、昔からほとんど変わっていない。“商材”だけが変わっていく」と言う。
例えば、「自宅で高収入」などの宣伝文句で増加傾向にある「内職商法」を見てみる。少し前なら、レセプト作成や宛名書きなどが代表的だったが、個人情報保護法の施行以来、レセプト作成は内職ではできなくなってしまった。そして、パソコンやワープロの普及で宛名書き内職も減った。
代わりに増えているのが、ホームページ作成やデータ入力などパソコンを使用したもの。仕事をエサに、パソコンや教材を高額で売りつけるといった悪質商法が多くなっている。
「悪質商法の業者は、時代を見る目に長けている」と、水口さんは言う。
例えば、IT起業がブームになったときには「未公開株」を、アフィリエイトがブームになったときには「アフィリエイトで稼ぐ方法」といった「情報商材」を販売する悪質販売が増えた。今後は、地デジのアンテナ詐欺などが増えるかもしれないと心配する声もある。
また、よく見られるが「一度被害にあった人が何度も被害にあう」というケースだ。これは、被害者の名簿が出回ってしまい、悪質業者から狙われやすくなっている、というのが理由の1つだ。
しかし、それだけでなく「一度騙された人は、何度も騙される傾向がある」。くれぐれも注意したい。