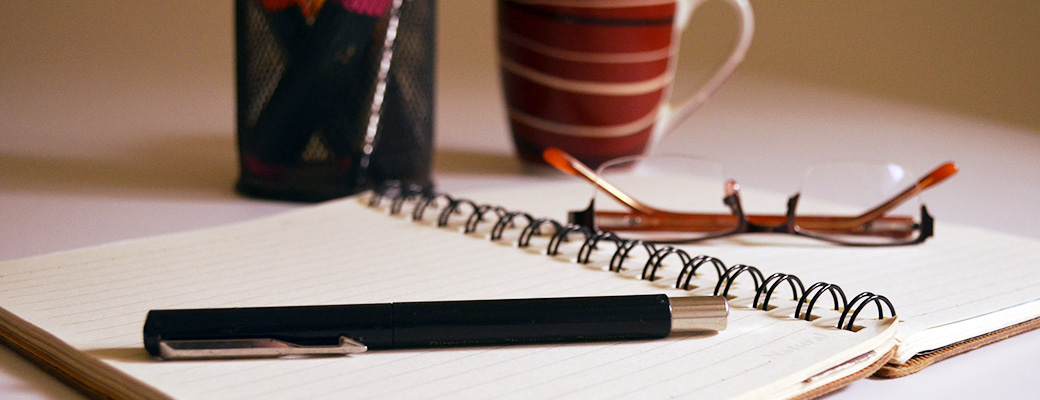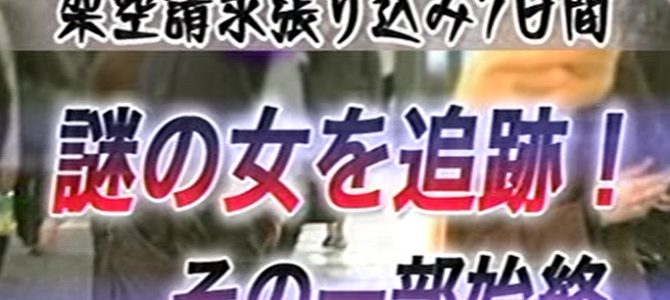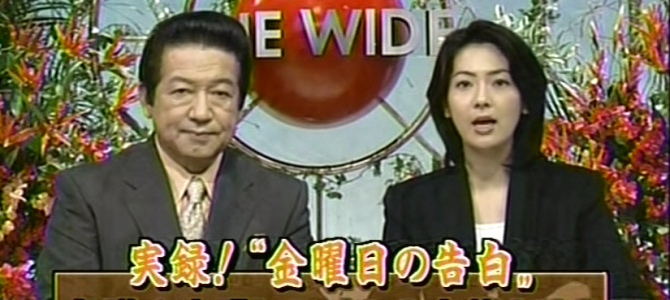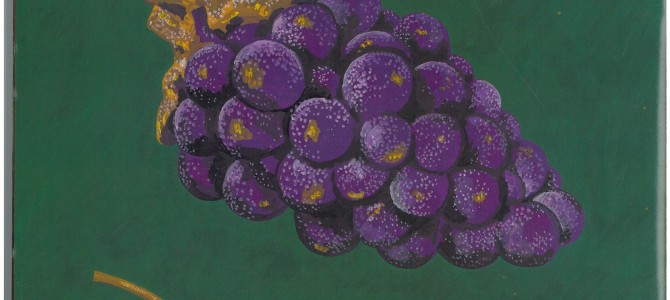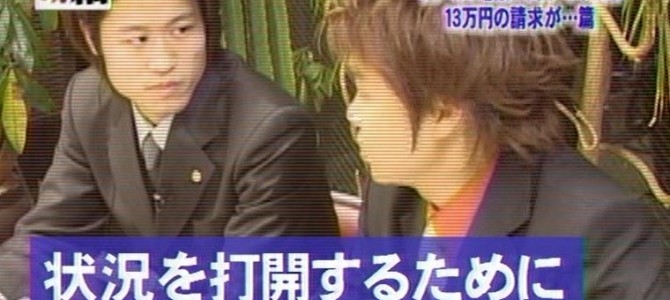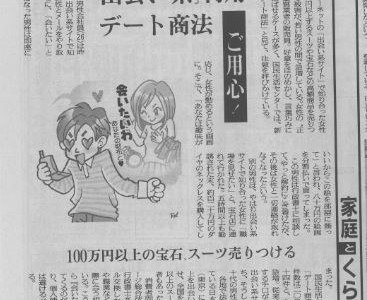男性には対応せず、女性には「裁判」を連呼する
新たな架空請求の手口とは
番組スタッフに、全く身に覚えの無い請求ハガキが届いた。そこには「電子通信料金の未納分がある」ので連絡するようにとあった。送り主は「日本債権管財教会」なる所で、連絡をしなければ、裁判になると書かれている。記載されている番号に電話をかけてみると、まず「IPコード」を読むように言われる。ここでスタッフがテレビ局名を名乗ると相手は電話を突然切った。そこで、別の男性スタッフがテレビ局名を名乗らずに電話をしてみると、またもや突然、電話は切られた。
そこで、さらに別の女性スタッフが電話をすると、今度は突然切ることは無く、やはり名前と分類コードを確認してくる業者。そして、「未納料金は2,800円で、すでに裁判になっている」と言う。何の料金かと訪ねても、「だいぶ前のものなので」とごまかし、続けて「もう裁判受理されていると思う」と「裁判」を強調する。そして裁判を撤回したいなら、今日の15時までに撤回費用を払えと言う。その金額68万円。これを弁護士に直接振り込めと続けた。さらに弁護士の名前を「ヒラツカツヨシ」と言う業者。撤回しなければどうなるのか?と尋ねるスタッフに、「出廷して裁きを受けることになる」と業者は言った。さらに、「裁判前だからこの金額で済んでいる」、「裁判が始まれば、もっと大きな金額が当然かかる」と不安を煽る発言を繰り返す。そして、スタッフが会社名を聞くと、ハガキに書かれている団体名とは違う名称を名乗った上、スタッフがその違いを指摘すると「裁判によって課が違う」等と説明した。
弁護士をかたって、不安を煽る発言を繰り返す悪質業者
最近では、集団での犯行が増えている
スタッフは、一度電話を切り、振込期限と業者が言った15時前に再度、電話をした。
スタッフが「不明点が多いので、お金は支払わない」、「不明点が多いのに、いきなり68万円を振り込めと言われても」と言うと、「振り込めなんて言ってないでしょ」と逆キレする業者。続けて、スタッフが「架空請求なんでしょ?」と問い詰めると、いきなり電話を切った。
その後、なんと「弁護士のヒラツカ」と名乗る男から、スタッフへ電話がかかってきた。しかし、この名前の弁護士は弁護士協会の名簿には載っていない。自称弁護士は「裁判が始まれば、あなたの立場が悪くなる」、「裁判の撤回をしなくていいのか?という確認の電話」だと言う。スタッフが「15時までに振り込むはずではなかったのか?」と尋ねると、自称弁護士は「そう、間に合う」と言う。続けて「時間外でも振り込んでもらい、明細書を法律事務所に送ってくれ」、「それで辞任する」と続けた。スタッフが、弁護士事務所名等を確認すると、はぐらかす自称弁護士。
架空請求は、以前は一人で行われることが多かったが、最近では集団での犯行が増えている。自称弁護士との電話を切った後、その前に話した業者から電話がかかってきた。
スタッフが「架空請求が増えているので、慎重になる」と言うと、「内入れ金でもいい」と請求額を50万円に下げ、執拗に請求してくる。さらに、第3の人物からも電話が。
「一部入金の件はどうするのか? 裁判取り下げる気があるなら…」と聞いてくる。スタッフは、「お金は支払いません」ときっぱり断ると、「弁護士の費用だが」と話が変わり「自分(業者)が30万円、ヒラツカ先生(自称弁護士)が50万円で決定した」、この金額を1週間以内に支払えと言う。何のお金か?とスタッフが尋ねると、自分達が動いた分と言う。最後には「司法で戦いましょう。家族、親戚に全て出す」と捨てセリフで電話を切った。
悪質な架空請求について、専門家に聞いた
悪質商法・消費者問題の専門家、エクステージ総合法務事務所・代表行政書士水口結貴さんに、悪質な架空請求について聞いた。このケースは、典型的な架空請求のケースであり、女性にきつく対応するのも、警戒心の無い人・信じてくれそうな人ばかりをターゲットにしているからだ、と教えてくれた。実際に、架空請求ハガキを受け取った人に聞いてみると、ハガキも段々、使う名称が有名弁護士や団体名を真似したものになったり、「督促状」等の赤い文字が大きくなっていくという。
自称警察官も登場
悪質架空請求詐欺の最新手口とは
警察庁によれば、2004年1月~2004年11月までの振り込め詐欺の被害は、222億円に昇る。架空請求・振り込め詐欺の手口は、ますます巧妙化している。
世間を騒がせている「オレオレ詐欺」。最近は、6人から詐欺の電話がかかってきたケースもある。例えば、息子を装った男から「大変なことをしてしまった…」と電話があった後、警察官を名乗る男から「息子さんが6歳の女の子をはねた」との電話があった。この電話を信じた57歳の女性は、保釈金として300万円を振り込んでしまった。さらに、女性の元に弁護士を名乗る男から電話があり「600万円で示談が成立したので、そのうち200万円を振り込んでください」と言われ、その後も保険会社や司法書士を名乗る人物から電話があり、合計で500万円近いお金を支払ったのだ。
スタッフは資料を集め、様々な架空請求業者に電話をかけた。架空請求ではないのか?と問うスタッフに「法務省の認定を受けている」と言う業者。中には、呼び出して実際に会って請求する業者も。
架空請求・振り込め詐欺に関しては、何よりも無視することが1番と水口結貴さんは説明する。そして、電話で個人情報等をしつこく聞かれた場合でも、不用意に個人情報を与えると、さらに電話がどんどんかかってくるなどの被害を呼んでしまうので、絶対に個人情報は教えないことを徹底するように、とアドバイスしてくれた。
ごく稀に、裁判上の支払督促・少額訴訟で請求がくる場合も
実際の裁判手続は無視しないで、すぐに法律家へ相談を
しかし、「ごく稀に、支払督促・少額訴訟といった、実際に存在する裁判手続を悪用して請求をしてくるケースがある。この場合は、異議申立をする等、対処をしなければならない」、「放置しておくと本人に不利益になってしまう」と、水口結貴さんは、新たな架空請求手口への注意点を教えてくれた。
さらに、架空請求と本物の裁判所からの書類の見分け方について、「裁判所からの書類がハガキで来ることは無い」、「『特別送達』という封書でくるので、わかると思うが、不安な場合は実物を持って警察や法律専門家、消費者センター等へ相談をすると良い」、「もし電話をする場合は、ハガキに書いている番号ではなく、必ず自分の住んでいる地域の裁判所等の番号を自分できちんと確認してから、連絡をするように」「たとえ、裁判所からの書類であったとしても、その日のうちに振り込めなどということはあり得ない」とアドバイスしてくれた。
また、特に狙われやすい人として
○以前に悪徳商法等の被害を受けたことがある人
このような人達の名簿「カモリスト」と呼ばれ悪質業者間に出回っている。
○結婚している男性
体裁・立場を気にして「アダルト料金の請求」・「出会い系サイトの請求」等と言われると人に相談しにくく、払ってしまう。
○20代~30代の女性
比較的使えるお金があること、女性の方が真面目にお金を払う傾向があるようだ。
もし架空請求などで対応に迷ったり、不安な場合はできるだけ早く、法律専門家に相談をするようにしたい。