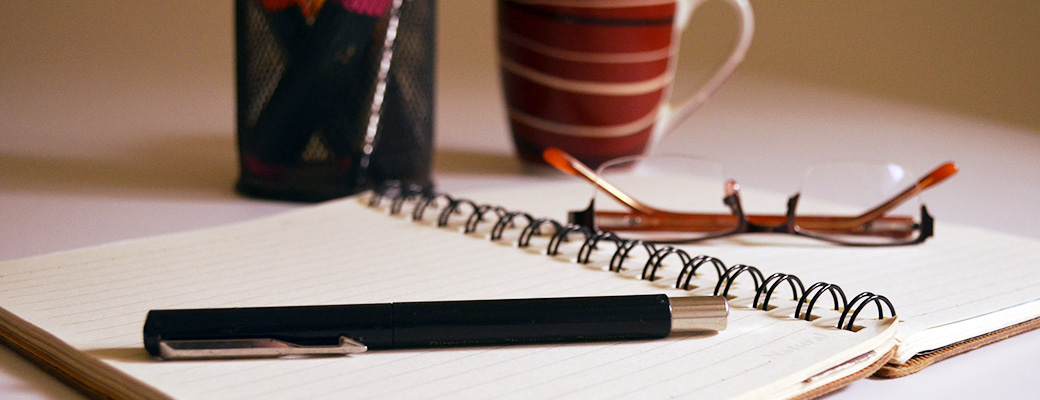「有名人に会える」などの釣り広告も登場
「マルチ商法」が若者に広がっている理由は?
マルチ商法のトラブルが学生に急増している。東京都消費生活センターによれば、平成15年度は相談増加が著しいということだ。消費生活相談員は、「若年層(学生)の相談が大変多くなっている」と言う。各大学で被害が止まらないようだ。また、商品別に相談件数をみると、健康食品が1位、次いで化粧品、食器・台所用品と続く。マルチ商法は「ネットワークビジネス」とも呼ばれ、特定商取引法では「連鎖販売取引」に該当する。専門雑誌も存在するほどだ。まず、自分が業者と契約して会員となり、自分が他の会員を紹介すると業者からボーナスがもらえるシステムになっている。但し、この「ボーナス」システムは業者によって異なるため、外からはネットワークビジネスの実態は分かりにくい。法律で禁止されている「ねずみ講」との違いは、「商品」を媒介にしている点だ。
某大学の学生に協力してもらい、マルチ商法のシステムを再現
リーダーはまず10万円で商品を購入。
その後、リーダーがまず2名を勧誘する。
勧誘された人も同じく、商品を1個ずつ購入する。
このように、次々に一人が2名ずつを勧誘していく。
会員が15名そろった時点で、リーダーには30万円のボーナスが渡される。これで、リーダーは20万円の利益を得た。
リーダーは、もしも自分のグループ内で勧誘することができない人が居る場合は、その位置に入ることもできる。ただし、その場合は改めて商品を購入しなければならない。
ボーナスを手に入れるために、リーダー自ら商品購入を重ね、結果負担が大きくなりやめられない。また、このシステムを続けていくと、いずれ日本の総人口を超えてしまうのだ。学生達は、「人を誘うのは無理そう…」という人もいれば、「10万円投資した意味がなくなるから何がなんでも捕まえる」という人もいた。
ネットワークビジネスでは、毎週のように「ミーティング」や「セミナー」が
開かれ、儲かる話が飛び交う
その場では、親戚や友人のリストを持ち1件1件に勧誘の電話をさせることも。TOPが借金をしてネットワークビジネスに投資している場合もあるため、「お前ががんばれば儲かる」という点を強調する。
ネットワークビジネスの説明会に連れて行かれると、その説明会では、イメージ的な話が多く、実際にネットワークビジネスを始めてから、支払のために借金を重ねる場合も多い。また、ネットワークビジネスのために大学で、皆からつまはじきにされる等の人間関係のトラブルにも発展する。
元マルチ商法の勧誘者がその実態を証言
「未成年取消」によって解約できたという、ネットワークビジネスの元勧誘者Aさんに話を聞いた。
Aさんは、高校時代の友人から「儲かる話がある」と電話を受け、(実際には、友人もその先輩から紹介されていた)最初に10万円を払って、ネットワークビジネスを始めた。Aさんは、この購入になんと学生ローンを紹介されていた。また、Bさんは、「自分達が入れば、上の人は儲かるわけだから、上の人は騙してでも入って欲しかったんだろう」と言う。しかし、実際には言われた程は稼げず、逆に「お金は無くなっていく一方だ」と言った。Aさんは、毎日セミナーに呼ばれ、それも大きな負担だったそうだ。「これだけ人がいるんだから」と安心してもらうための「サクラ」だったと思う、とAさんは続けた。友達関係にも気をつかわなくてはならず、「おかしくなりそうだった」と二人は口を揃えた。
合法のマルチ商法にも、規制がある
合法であっても、マルチ商法(連鎖販売取引)には当然、規制がある。例えば、不当な勧誘行為やクーリングオフ妨害行為の禁止、契約前の概要書面交付、契約後の契約書面の交付の義務等だ。また、業者はクーリングオフ制度を儲ける義務もある。
再び、元マルチ商法の勧誘者が、勧誘トークを証言
Aさんは、喫茶店に呼び出されると、先輩と自分の知人、さらに別の先輩…が待っており、なぜか、3人にさせられた。すると一人が「健康になれて、儲かる話がある」と始め「詳しくはこちらの人から…」と先輩が説明を始めた。まず「簡単に儲かる、という話があったらどう思いますか?」と興味を引き、その後は商品の成分等、難しい説明に入ったという。また、「例えば、1億円企業と呼ばれるものが、カラオケとして『命』は無ければ困る。『予防する医療』・『ガンの予防に効く』」・「ビジネスチャンス」等と言われる。「ビジネスチャンス」と言われた時点で、彼らは消費者(商品を選んで買う人)からユーザー(マルチ商法の商品を買う人)へ立場が変わってしまった。
また、勧誘者は「10万円(商品価格)で何ができますか?」と問いかけてきて、普通に暮らしていれば、そのうち消えてしまうが「このビジネスに10万円を投資して、将来のために役立てたらいいじゃないですか?」と押してくる。業者内には「誘う時には会話の主導権を握らなくてはいけない」というマニュアルもあるそうだ。
そして、「この仕事やるよね?」と、やって当然の雰囲気に飲まれてしまうのだ。そして、入会後は、このようなマニュアルの存在を知ったとしても、すっかり自分も「これでいけるでしょ」と「勧誘者」の立場に変わる。
消費者問題に詳しい法律家に聞く、ネットワークビジネスの問題点とは
自らも、ネットワークビジネスの勧誘現場に潜入したこともあるという、消費者問題の専門家・行政書士エクステージ総合法務事務所、水口結貴行政書士は、「自分のこれまでの立場を一度否定して、本人が混乱した所に、新しい教え・(マルチ商法で言えば、新しい金儲けの手段)を植え付けていく」と解説する。
学生達は「友人関係があると入ってしまいそう」、「10万円払っても30万円入ってくるなら、絶対やる」、「最初は『失ってもいい』という友人から声をかけて、ダメだったら親友でも声をかける、そして最後は親にも言う」といった感想。
「金を貸してくれ」と言われたら、即、断るとしても「金儲けなんだ」と言われたら、つい聞いてしまう、その心理に巧みにつけ込むトークには十分、注意したい。