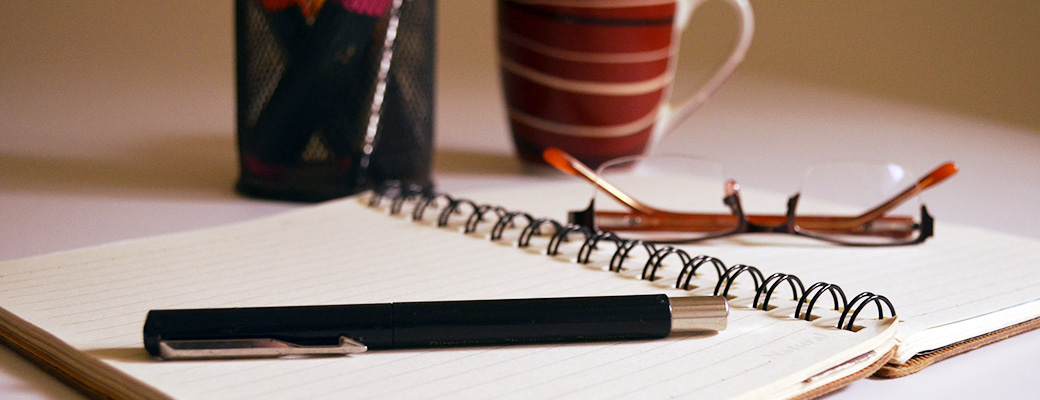キャンパスで被害拡大
激撮!“マルチ”勧誘~ネットワークビジネス~
首都圏の大学で「学生が学生を誘う」マルチ商法被害が増えている
これまで、何度も問題になってきたマルチ商法。今、その勧誘が大学のキャンパスへと広がっている。勧誘の現場にカメラが潜入した。都内のある区民ホール。そこに20才前後の若者が次々と集まっていた。彼らは皆、身だしなみを整え、スーツ姿の者も多い。
着席した彼らの前に同世代の者が姿を現した。そして、「ネットワークビジネス」の素晴らしさを伝えるのが、このセミナーの目的だと言う。
会員を増やすことで「利益が得られる」
これは、マルチ商法の勧誘セミナーだった。「マルチ商法」の被害が今、学生の間で広がっている。
マルチ商法の被害者に話を聞いた
被害者の学生Aさんに話を聞いた。「時給にしたら、1800円くらい。週に1~2回で7~8万円稼げる」と言われた。しかし「実際は、全然違っていた」そうだ。都内の大学に通うAさんは、マルチ商法に10数万円をつぎこんでしまった。
予備校時代の友人から「久しぶりに会うのでご飯でも」と誘われたことがきっかけだったという。それがどんどんネットワークビジネスの話になっていったそうだ。半ば強引に誘われた、マルチ商法のセミナーだったが、そこでAさんは、マルチ商法の罠に引き込まれていった。
セミナー会場で「自分でもできる」と錯覚する
壇上の女性が、成功談を話し出した。「先日、20万円を入った財布を落としまして。ああ、私、20万円を持てるようになったんだわ、って」。
そのうち、ビジネスのシステムの話になっていった。繰り返される景気のいい話。さらに信憑性を高めるためか、こんな話も飛び出した。
このシステムは「マサチューセッツ工科大学の経済学部の学部長さんが考えたシステム」だ、という。
さらに、「アメリカの大統領は、ネットワークビジネスを取り入れて、わが国の経営が良くなったと」言っている、という。
さらに、ある計算式によれば、「月の収入が496万円」にもなる、という。
こんな説明を聞かされた学生は、次第に「自分でもできる」と思い込むようになる。
勧誘の場を「喫茶店」に移し、クロージング
勧誘の場はここでは終わらない。前にアドバイザーの男性が出て来ると、「この後、質疑応答の場として喫茶店に来ていただいて」…と次なる会場を案内する。
そして、外に出ると「サポート要員」として、多くのスーツ姿の男性たちが待機していた。通称「アフター」と呼ばれる「個別勧誘活動」のためだ。
勧誘する側とされる側が組になって散っていった。その1つを追いかけると喫茶店へ入っていった。
そこでは、アドバイザーが「成功する」、「やりやすい」など、ビジネスの魅力を語っていた。
「A・B・C」と呼んで、座る場所まで決めて
マルチ商法を契約させる
こうしたクロージングの場では、座る場所まで決まっている。
例えば「A」は「アシスタント」。すでにビジネスにどっぷりハマっていて、勧誘トークをするベテランだ。
「B」は「ブリッジ」。上位者と新しく入っている(新入者)を橋渡しするのが役割だ。
そして「C」が「カスタマー」。新しくビジネスに加入する学生だ。
通常、アシスタントの話に集中させるため「カスタマー」は店の入り口を背にして座らせる。
「まず3人から10人に増やそう」、「そして10人になったら、100人を目指そう」。
学生はここで初めて、システムの説明を受ける。
ネットワークビジネスとは、次のようなシステムだ。
●商品を買って会員となり、商品を他人に売ることで利益を得る
●自分が売った人物がさらに他人に商品を売れば、自分にもボーナスが入る
勧誘側は「ローリスク」、「ハイリターン」などと説明する。この日、店内の半分は「アフター」の若者で占められた。誘う側も多くが学生だ。彼らの成功談を聞くたびに、誘われる側もビジネスの成功談を信じるようになる。
お金を持たない学生には学生ローンで借りてでも契約させる。
そして、会員を続けるためには商品を購入し続けなければならない。
そしてAさんが勧誘できたのはたった一人。これでは全然お金が入ってこない。彼は13万円を使ったという。
なぜ、大学生はマルチ商法にはまるのか?
専門家に聞いてみた。すると、今の学生の就職環境が大変厳しいため「サラリーマンになるくらいなら、“自分で自立して超一流ビジネスマンにならないか?”、“世界を股にして活躍しないか?”と言われると、非常に耳障りがいい。
巧みな話術を信じこむ学生たち。勧誘セミナーの内容に問題はないのか?
悪質商法に詳しい、エクステージ総合法務事務所 代表行政書士 水口結貴さんに聞いた。
例えば、「月にこれくらの収入になる」とか「月に500万近い収入がある」とか、言っている場合は、「断定的な判断を提供している」ので、「消費者契約法で契約解除ができる」と教えてくれた。
さらに、業者は「アルバイトと言っておきながら、ビジネスの話をしている」、「まったく違う話をしている」。
これは「嘘」を言っているので「不実告知」になる。不実告知は消費者契約法の中で「してはいけない」ことになっている。オーバートークが目立つ、と指摘する。
マルチ商法の被害はお金だけに留まらない。誘えない人がいなくなる手あたり次第に声をかけるようになる。会社側は学生同士の勧誘については、今後指導をしていく、という。会社側は最後までシステム自体には問題がないと主張する。